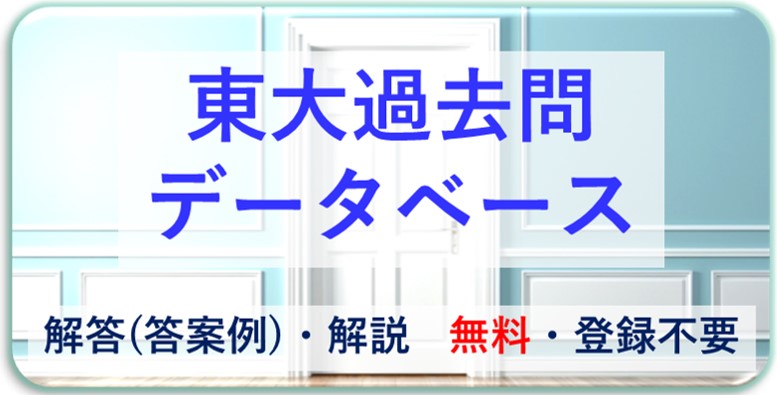2025年東大日本史(第1問)入試問題の解答(答案例)と解説
東京大学の日本史の設問を「リード文」「設問」「資料文」それぞれで分析しています。
目次
リード文の分析
特にありません。飛ばします。
設問の分析
時代設定は「7世紀から8世紀にかけて」。大雑把に言えば、飛鳥時代から奈良時代にかけてですね。
問われているのは「中国文化の受容のあり方や担い手はどのように変化したか」という点と、「その背景には何があったか」という点。2点です。
気を付けてください。中国文化の受容の「あり方」です。「あり方って何!?」といつも思います。作問者として、曖昧なままにできるので都合の良い表現なのでしょう。要するに、こちらで勝手に出題者の意図を読み取らなければなりません。
背景については、資料文を解説しながら書いていきます。
資料文の解説
資料(1)
知っていることが書いてあります。
法隆寺金堂釈迦三尊像が鞍作鳥によってつくられたことや北魏様式であること。飛鳥寺が蘇我馬子によってつくられたことや、百済王が技術者を派遣したこと(ここはやや細かい知識か)など。事前の勉強で知っていることが多いと思います。
こういう場合は、設問で問われていることに即して、要素を引っ張り出しておくことが大事ですね。
中国文化の受容のあり方
法隆寺という聖徳太子が作った、この時代を象徴するお寺が渡来系氏族によってつくられていると書かれています。つまり中国文化の受容は渡来人によりもたらされています。
北魏様式というのが良くわからなくても、中国の魏から来たのかなくらいの推測ができれば、中国文化であることが分かるでしょう。
続いて、飛鳥寺に関しても百済王が派遣した技術者が関わっていますし、鞍作鳥も仏像を作っているとのこと。これも日本古来の技術ではなく、渡来人によってもたらされた技術であることが分かります。
なお、もたらしたのは朝鮮半島出身ですが、技術そのものは中国のもの(北魏様式)であると区別して理解することもできますね。
また、中国から受容した内容としては、お寺や、お寺の中にある金堂、仏像などですね。これは資料(4)(5)と比較すると明らかに違う内容なので、覚えておいてください。
中国文化の受容の担い手
担い手には2通りの解釈があると思いました。
まず、日本へ文化を伝えた人について。これは上述したように渡来系の人ですね。
一方、文化を伝えられた人は、聖徳太子と蘇我馬子が指摘されています。これは当時の権力者ですね。先に行ってしまいますが、資料(3)~(5)からは、文化を受け取ったのが個人ではなくて国家そのものであると読み取れます。ここが対比されているようです。
背景
では、なぜ渡来人が中国文化をもたらしたのか。その背景を考えると、シンプルに百済が日本の友好国だったから、と言えるでしょう。百済は大陸において、日本の拠点でしたから、そこから文化が伝来するのは自然です。
資料(2)
次に資料(2)ですが、これも知っていることが書いてあると言ってよいでしょう。
法隆寺の金堂の壁画がインド的な要素が見られて、初唐の絵画様式を使っているとか、新羅を通じて唐の文化が受容されたとか、亡命した百済人が活躍したとか。もちろん知っていることも大事ですが、これをわざわざ資料で書いてくれていることがありがたいわけですが。
中国文化の受容のあり方
法隆寺の金堂壁画にはインドの要素や初唐の影響があります。この時期には唐文化が受容されたとも書いてあります。つまり引き続き中国文化を受容しているということです。北魏様式から唐の文化に代わっていますが、これは王朝が変わったので当然ですね。資料(1)と特に違った特徴は読み取れませんでしたが、資料(1)では623年に対して北魏様式で、資料(2)では670年に対して初唐なので、読み取ろうとすれば、やや古い時期(昔の時期)の中国文化の影響を受けているとも言えるでしょう。
また、受容している内容としては、資料(1)と同様でお寺や壁画などですね。
中国文化の受容の担い手
日本に文化を伝えた人は、百済人から新羅へ変わりましたね。受け取った人は、聖徳太子しか登場しないので、資料(1)と同様、当時の権力者や特定の個人などと言ってよいでしょう。
背景
背景としては、ヒントになることが書いてあります。白村江の戦いです。
白村江の戦いの直前に、朝鮮半島の拠点であった百済を失い奪還しようとするも跳ね返され、668年に唐と新羅の連合軍が高句麗を滅ぼします。こうしてしばらく中国大陸に唐と新羅の2国が並ぶ時代が続きますね。
そりゃ当然、白村江の戦いの前には百済人が来て、戦後には百済人が来なくなるわけです。ではなぜ白村江の戦いの後には新羅が来たか(唐は来なかったか)
やや突っ込んだ説明をしますが、白村江の戦いの後、唐と新羅の関係が悪くなり、新羅が日本に接近してくるのです。
というのも、唐と新羅が争っているということは、敗戦国の日本がどちらに着くかによって有利な方が決まるという「おいしい」ポジションになったからです。最も弱い日本が大陸のキャスティングボードを握ることになったのです。この状況で新羅は日本に接近して、唐は日本から離れていく、ということになったので、新羅から文化が受容されたのです。
ここまで詳しいことを答案に書く必要はありませんが、知っておくと他の東大の過去問を解く際にも理解が深まってよいですよ。2009年の第1問とか。
資料(3)
この資料だけ、文化の内容が入っていません。
書いてあるのは、遣唐使が派遣されて、中国皇帝に国号「日本」を承認してもらったということと、唐に対して20年に一度朝貢する約束をしたことです。しかし、背景知識を足すと、文化の受容に関わってきます。
まず朝貢について軽く説明。他の解説記事でも書いていますが、朝貢というのは中国の属国になるわけでも、下の立場になるわけではありません。
日本から唐に朝貢したとき、儀礼として皇帝に臣下の礼を取りますが、これは友達の家に行って玄関を上がるときに「お邪魔します」と敬語を使うようなものだと思えば良いでしょう。自分が下になったわけではなく、皇帝に謁見するんだから、礼儀はしっかりしておくというだけです。
では朝貢とは何かといわれると、「文化的な交流を伴う貿易」くらいに思っておけばよいと思います。
国号「日本」を承認してもらい、20年に一度朝貢する約束をしたということは「日本」と「唐」が貿易や交流をするという約束をしたということです。
問われている「文化の担い手」には「伝える人」と「伝えられた人」がいるという話がありましたが、今後は(聖徳太子や蘇我氏など)個人ではなく、日本という国家も文化を受容することになったと言えるでしょう。
なお、この背景としては、8世紀頃になると唐と新羅の関係もやや安定してきて、唐も日本と国交を結ぼうと思うようになったことを補足しておきましょう。新羅とも継続して交流はありますが、唐とも20年ごとに朝貢する約束をするくらいなので、継続した関係をお互いが認めているわけですね。
資料(4)
ここまでとは様子の違うことが書いてあります。一つずつ整理しましょう。
中国文化の受容のあり方
道慈が批判する内容を見ると「多くの僧尼が正式な戒を授かっておらず、今の日本の仏教のあり方は、唐とは異なる」。また受容した内容が三論宗や法相宗、経典五千巻余りとのことです。
資料(1)(2)では、お寺やそこにある金堂、壁画、仏像などを受容しましたが、資料(4)では経典や戒(を授かっているかどうかを気にしている)に変化しています。
これを抽象化すると、有形のものから無形のものになったとか、表面的・形式的なものから、実質的なものに変わったとか、仏教理論を大切にするようになったとか、色々な言い方が言えると思います。
中国文化の受容の担い手
担い手も変化しています。
まず、文化を伝えた人ですが、道慈や玄昉という日本人の留学生(学問僧)に代わっています。資料(1)(2)は日本人ではなく百済や新羅の人でしたから、日本人が自ら主体的に中国まで学びに行っているというのは変化ですね。
伝えられた人は明記されていませんが、三論宗や法相宗、経典が伝わったということは、特定の個人というより、多くの人が関わりそうだなということくらいは読み取れますね。
背景
背景としては、資料(3)で書いたように、唐と日本が国交を結んだことで日本からも勉強しに行くようになったということが分かれば良いでしょう。
資料(5)
資料(4)と合わせて読むと分かりやすいです。
中国文化の受容のあり方
資料(4)から継続して、戒を伝えるとか、授戒するとかそういう話がありますね。つまり仏教の本質的な部分へと受容の仕方が変わっていると言えるでしょう。なお、一言ではありますが「仏像製作などの工人も伴ったらしい」とありますから、資料(1)(2)の時代と同じで仏像なども引き続き受容しようとしています。(まあそんなの教科書レベルの知識があれば知っているのですが)
気になるのは、東大の先生が書いた資料(5)の書きぶりです。「経典や戒律をもたらしたほか、仏像製作などの・・・」という書き方をしています。つまりメインが「経典や戒律」で、「仏像製作」はサブとして捉えられているんですね。
中国文化の受容の担い手
「伝えた人」として登場するのは、鑑真です。書いてある通り鑑真は「唐の戒律学の継承者」ですから、当然日本人ではなく唐の人です。資料(4)では日本人の留学生や学問僧が登場しましたが、ここでは唐の人が文化を伝えたと出ました。
資料(1)(2)では渡来系の人でしたから、対比して「7世紀には中国文化を百済や新羅など渡来人から間接的に受容したが、8世紀には唐に学んだ日本人留学生や学問僧、または唐の僧侶から直接文化を受容した。」などと、間接→直接というように書いても面白いですね。
伝えられた人としては、聖武天皇という権力者以外にも、多くの僧侶が授戒したことが書いてあります。後述しますが、鎮護国家思想を採用し、仏教によって国を治めようという方針があったわけですから、国家が受容したと理解しても良さそうです。
背景
聖武天皇は国分寺や国分尼寺を全国に作るなど、仏教の力によって日本を治めようとしていました。鎮護国家思想です。
そのため、聖武天皇が授戒したということは、鎮護国家を推進する一部だと捉えても良いでしょう。
まとめの表
簡単ではありますが、以上の内容を表にしてみました。これを元に答案を作成してみましょう。

答案例
7世紀前半は友好関係の百済、白村江の戦い以降には新羅を通じて渡来人や亡命者から間接的に、有力氏族に対して絵画や仏像など有形の文物が伝わった。8世紀には律令国家が唐に朝貢する形式に変化したことで、留学生や渡来僧が直接、国家に文化を伝えるようになり、経典や戒律など仏教理論を積極的に受け入れた。
【さらに深く学びたい方のために】
敬天塾では、さらに深く学びたい方、本格的に東大対策をしたい方のために、映像授業や、補足資料などをご購入いただけます。
ご興味頂いたかたは、以下のリンクからどうぞご利用下さい。

解説.jpg)