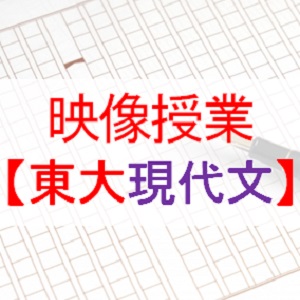2025年東大国語 第1問 田中彰吾『身体と魂の思想史ー「大きな理性」の行方』解答(答案例)・解説
2023年の「仮面と身体」、2024年の「時間を与えあう」に続き、今年の第1問も非常に論理的な文章で、かつ研究内容が詳細に書かれている文章でした。
研究内容が書かれているということは、論理的な文章であるということにも通じますので、ロジカルに考えられる受験生にとっては容易に感じやすいでしょう。現代文の指導でも、文法構造などから論理的に読む訓練をされている受験生も多いと思われるため、取り組みやすかっただろうと評価をしています。
毎回書いていますが、現代文は回答者によって解釈のブレ、答案の表現のブレなどが激しい科目であるため、賛否両論が発生することは承知していますし、闊達な議論を奨励しています。
お気づきの点がありましたら、遠慮なくコメントをお願いします。
目次
敬天塾作成の答案例
敬天塾の答案例だけ見たいという方もいるでしょうから、はじめに掲載しておきます。
受験生の学習はもちろん、先生方の授業にお役に立てるのであれば、どうぞお使いください。
断りなしに授業時にコピペして生徒に配布するなども許可していますが、その際「敬天塾の答案である」ということを必ず明記していただくようお願いします。
ただし、無断で転売することは禁止しております。何卒ご了承ください。
【平井基之のサンプル答案】
設問(一)
生後一年ごろまでの乳児は、視覚によって得る情報と自分の身体に生じる感覚とを結びつけることが出来ないため、鏡像を自分であると認識せず、他人として知覚するから。
設問(二)
鏡像認知ができるまでの移行期の乳児は、まだ視覚からの情報と身体の感覚とが結びつき始めたばかりであるため、それらが結合していることを奇妙に感じて当惑してしまうから。
設問(三)
チンパンジーは群れの中で仲間の身体を観察しながら、自分の身体の見られ方を学習することで、自分の客観的な姿のことを知っているため、鏡像と自分とを重ね合わせられるから。
設問(四)
自分の身体を認識するには、視覚からの情報と身体の感覚とを結びつけるだけではなく、他人を観察しながら、他人からどう見られているかという点に気づくことが必要であるため、自分の姿に対する自覚には他人からの印象や評価が深く関わっているということ。
※多少、字数が多めの答案になっていますが、短くまとめきれない私の力量不足以外の何物でもありません。あくまで、答案サンプルの一つであり、皆さんの考察の材料となることを願って作成したものですので、寛大な心でご覧いただけると幸いです。
設問(一) 鏡像を遊び相手として扱うような振る舞いを見せる

採点は5段階評価で標準を3とし、
難しいポイント1つにつき+1、
簡単なポイント1つにつき-1としています。
「傍線部の構造」は答案骨格の作りにくさです。
「表現力」は自分の言葉に言い換える難しさです。
一番簡単!?
難易度判定のレーダーチャートを作ったら、なんと過去一番の簡単な判定に!そんなに簡単だったっけ?ともう一度判定しなおしてみると、やはり簡単。
「どういうことか」ではなく「なぜか」の問題なので、傍線部の構造に対する評価が甘くなるのを差し引いても、それほど難しくはないですね。字数制限も緩いし、自分で表現しなければならない部分(言い換え)もそれほど難しくない。
一番難しいのは要素の場所を発見することですが、これも別に苦労するわけではない。
練習問題にとても良いですね♪
オマケ:発達段階ごとの呼び方
オマケではありますが、乳児や幼児の違いは分かりますでしょうか。
私にも子どもがいて保育園に預けていたこともあるので、知っていたつもりでしたが、改めて調べてみると、児童福祉法で決められているようでした。
新生児:生後28日以内
乳児:1歳未満
幼児:満1歳~小学生未満
とのことです。
なお、児童や子ども、少年など、いわゆる子供に対する呼称はたくさんあるようで、しかも法律ごとに定義が違うらしくややこしいようです。
こちらのリンク先を参照
乳児と幼児は、母子健康法でも定義されているようですが、児童福祉法と同じ定義のようですね。
「乳児も幼児も同じだろう」と思ったのか、再現答案では乳児のことを幼児と書いているものもありましたが、用語は正確に使うのが旨です。注意しましょう。
冒頭3行にヒントがいっぱい
傍線部は、本文の3行目にあります。
注目ポイントは、直後の「のである」という表現。これは、「のである」が存在する文の1つ前の文を補足する表現です。つまり、「生後1年ごろまでの乳児は、鏡にうつった身体を他者として知覚している。」に呼応しているということです。
しかもここが、問いに対する答えに該当します。「鏡像を他者と知覚しているから、遊び相手として扱う」という論理が成立しますね。なのでまず、ココを書くことが決定。すぐ見つかります。
しかしこれでは、なぜ鏡像を他者と知覚するのか、説明がありません。そこでさらに遡ってみると、本文1行目に「鏡像を自己として認知できるようになるには、生後1年半~2年程度の時間がかかるといわれている」とあります。まとめるなら「発達が十分でないから」とか「鏡像を自分だと認識できるほど発達していないから」などと考えられます。
ここまでをまとめると
「発達が十分でなく、鏡像を他者と知覚しているから」と答案が書けますね。
短すぎて困る
なんとなく要素を探しきった気になるんですが、ここで問題が。答案が短すぎる!!
これではさすがに短いので、他にないかを探してみます。
すると、傍線部の直後は、「14か月ごろから・・・」と発達段階の違う話が出てくるのでスルーするのですが、さらにその後、次段落の冒頭に「生後間もない乳児にとって」とあり、もう一回該当する発達段階の話に戻ってきます。
そして第2段落5行目に「つまり、生後1年ごろまでの乳児にとって」とあり、ココにも傍線部に対する理由があります。
曰く、「身体に由来する体性感覚的な情報と、外界に由来する視覚的情報とは分断されており、いまだ統合されていない」。これだけあれば字数も十分でしょう。ということで、これらをまとめて、言い換えるべき語を言い換えたら答えです。
別のアプローチ
上記では、「答案が短すぎて困る」というアホくさい理由で説明しましたが、(いや、短いのは困るので、悪いアプローチではないんですが)もう少し真面目なアプローチをしてみましょう。
冒頭3行をまとめた答案を再掲すると
「発達が十分でなく、鏡像を他者と知覚しているから」
となりますが、これだけでは、なぜ発達が十分でないと鏡像を他者と知覚できないのか、説明できていません。つまり、冒頭3行をまとめただけでは、説明できているようで、論理が不十分で説明が出来ていないのです。
そこで、この不十分な論理を補うために、他の要素を探すと・・・と考えて、視覚的情報やら体性感覚やらを探し当てても良いでしょう。
なお、このように論理が不十分だとして、論理を補うように要素を探す(もしくは、自分で補う)という考え方は、東大現代文で(特にここ最近)頻繁に用いますね。ぜひ身に着けたい技法です。
平井答案の解説
生後一年ごろまでの乳児は、視覚によって得る情報と自分の身体に生じる感覚とを結びつけることが出来ないため、鏡像を自分であると認識せず、他人として知覚するから。
・ほぼ上述した通り。見つけた要素を、論理が整合するように並び替えたのがメイン作業です。
・「視覚的情報」と「体性感覚的な情報」は、抽象的かつ筆者の個人言語であるため、平易な言葉に言い換えています。
・実は上述していないポイントがまだあります。「視覚の情報と体の感覚を結び付けられない」と「他人として知覚する」の間の論理も飛躍しているように感じてしまったので、「鏡像を自分であると認識せず」と補いました。もしくは本文の冒頭にも同趣旨の内容があるので、そこから引っ張ったと考えても構いません。
設問(二) 鏡像認知が成立する途上の移行期に、鏡像を回避する行動が見られる
要素は傍線部の近くにあるのだ。これは絶対の法則なのだ! ←本当に?
敬天塾は、現役生や浪人生以外にも、仮面浪人や社会人受験の生徒さんもいらっしゃり、人数は少ないものの多様性があります。
募集対象も全国・・・いや世界。オンライン塾なので色んな学校出身の生徒さんがいますし、多浪の生徒さんの中には、大手の予備校をいくつか通ってから敬天塾にという方もいらっしゃいます。しかも個別指導がメイン。
となると、そりゃあまあ、いろんな塾や学校、予備校の先生たちがどのような指導をされているのか、様々な情報が集まってきます。
一方で僕は理系上がりの人間なので、文系科目において一般的にどのような指導が現場でなされているのか知らないところからスタートしています。そこで、生徒を指導していると共に、生徒からも色々教わるのです。多くは「なるほど~」と膝を打つようなものなのですが、中には「ええ?本当に?」と疑ってしまうものもあります。
その1つが「傍線部の前後(特に前)にある要素をくまなく探してまとめれば答案になる」というもの。
確かにそういう問題もありますし、多いと言えば多いのかもしれない。でも決めつけちゃって大丈夫?絶対ではないですよね。というのが僕の感想です。
「現代文の文章は、必ず傍線部の近くに要素があるように書かなければならない」みたいなルールがあるなら別ですが、んなわけない。
しかも傍線引く場所は東大の先生が決めています。そう、恣意的に場所が決められているのです。
つまり、東大の先生がそういう問題を出題しているわけであって、東大側が出題傾向を変えたら崩れてしまいます。
この問題が、まさにその典型。傍線部の近くに要素がありません。
たまたまなのか、意図的なのか。そのあたりは各々の分析に任せますが、いずれにしろ「傍線部の近くだ!」と思い込みすぎると痛い目に合うので、気を付けましょう。
ここで突然、心の一首
文を読み
文意や趣旨を
理解して
問いの答えを
簡潔に書く
やはり、文章をしっかり読み、構造を理解し、論理や文脈を柔軟に解釈して、問いに素直に、簡潔に答える。これだけだと思いますね。
傍線部から離れて不安になった頃に要素が登場
では、解説を。
傍線部の段落が「両者の統合過程において、何が起きているのであろうか」とあり、前段落とは違う話題を展開しようとしていることが分かります。
しかも疑問形。「何が起きているのであろうか?」とwhatで聞く疑問文なので「自分で聞いておいて、自分で答えを言う法則」が発動。その答えを導くように、この後の論が展開されます。
傍線部は「鏡像認知が成立する途上のの移行期に、鏡像を回避する行動が見られる」とのことです。「移行期」と「鏡像を回避する」という情報をしっかり覚えて、その原因が書かれている部分を探します。
なお、この時点で傍線部より前に要素がないことはハッキリしていますね。
傍線部の後を読んでいくと、「これは別の研究でも確かめられている」と、並列の内容が登場。傍線部の理由はなさそうです。
この段落はこのまま終わり。次段落は「鏡に対する回避的な反応が生じる以前」おありますから、「移行期」ではありません。中身を見ていても「鏡像認知ができる前は視覚情報と体性感覚が結びつかない」とか、「鏡像認知ができた後は連合している」とあり、第2段落と同趣旨の事が書かれているだけ。移行期に回避する理由は書かれていません。
「あれ~、理由が書かれてないなぁ」と不安になりながら、さらに次段落まで読み進めると、やっと移行期の話に!
「移行期の乳児にとっては、鏡像はどっちつかずの中途半端な存在」とか「どのように受け止めてよいのかいまだ正解が見当たらず」などが発見できます。
決定的なのは「これが落ち着きのない回避行動を引き起こす原因になっているように見える」という記述です。もうこれは、傍線部の答えがここにありますよ、と言っているのと同じです。
ということで、この部分を簡潔にまとめれば答えです。
平井答案の解説
鏡像認知ができるまでの移行期の乳児は、まだ視覚からの情報と身体の感覚とが結びつき始めたばかりであるため、それらが結合していることを奇妙に感じて当惑してしまうから。
・上述した内容でほぼ説明は終わりですが、工夫としては最後の「当惑してしまうから」の部分です。本文中には「どのように受け止めてよいのかいまだ正解が見当たらず」とありますが「どのように受け止めてよいのか」がぼやけた表現なので、より直接的な表現の方が良いだろうということで、「当惑」としました。
・もう一つ工夫したポイントとしては、「中途半端」の言い換えです。視覚像が体性感覚と結びつかない状態から、結びついている状態の真ん中であることと、奇妙に感じるとか当惑してしまうとかに結びつけるのに良い表現は何かと考えたところ「結びつき始めたばかり」となりました。まだ結びつき始めたばかりだから、その状態に慣れていないので奇妙に感じ、当惑してしまうと表現したということです。
設問(三)そこに映っている・・・気づくことができる

まずは文法から攻めよう!
傍線部の冒頭「そこ」があるので、中身を探りますが、鏡であることは明らかでしょう。
傍線部が含まれている一文を見てみると、「からこそ」とあります。これはラッキー。傍線部の理由がかかれているのは「からこそ」の前の部分ですね。
読んでみると「群れで育ったチンパンジーは「他者から見た自己の身体」を最初から知っているからこそ」とあるので、この部分は使うことが確定。しかしこれだけでは理由として不十分。なぜ群れで育つと「他者から見た自己の身体」を最初から知っているのかが分かりません。そこで、さらに理由を探すことになります。
ところで、傍線部の直後を見てみると、またまた「のである」があります。設問一と同様に、傍線部よりもう一つ前の文を説明しているので、遡ってみてみましょう。すると「チンパンジーは成長の過程で「自己から見た他者の身体」と「他者から見た自己の身体」を交換すること。自己の身体が外的な視点から見るとどのように見えるのかということを学習すること、が書かれています。
この部分は傍線部の理由に該当しそうですね。
そこで論理を整理してみると、
群れで育つと、「自己から見た他者の身体」と「他者から見た自己の身体」を交換する (「交換」は比喩表現なので、答案では言い換える)
↓
自己の身体が外的な視点から見るとどのように見えるか学習する
↓
最初から「他者から見た自己の身体」を知っている
↓
鏡像が「外的視点から見た自己の身体」であると気づける ←傍線部
これをまとめれば答案になります。
論理を追うだけなので、それほど難しくはないですね。
視覚情報と体性感覚の統合を入れるか、入れないか
ここで疑問が一つ。
傍線部が含まれている段落(第7段落)の冒頭にこうあります。
ここから推測できるのは、鏡像認知が単に「ここ」で生じる体性感覚と「そこ」に見える視覚像との連合だけで成り立ってはいない。
ということは、鏡像認知ができるためには、条件が2つあるということです。
1つは、視覚情報と体性感覚が連合すること。
もう1つは、上述したように「自己から見た他者の身体」と「他者から見た自己の身体」を交換して、「他者から見た自分」の見え方を学習すること。
傍線部の内容を大雑把に要約すると「チンパンジーが鏡像認知できる」であり、その理由を答えるわけですから、「視覚情報と体性感覚が連合しているから」というのも含まれることになります。
一方で、字数制限があり、これを入れようとすると厳しい。
そしてもう一つ。もう視覚情報とか体性感覚とか、設問一と二で書いてます。わざわざここで再度書く必要があるのか、という疑問も頭をよぎります。
ということで、以下の私の解答では、両方作成しました。
結果として、表現を簡素にすることで、字数制限の壁を突破し無理やり要素を詰め込みました。いかがでしょうか。
平井答案の解説
(解答例1:視覚情報と体性感覚の結合をいれない)
チンパンジーは群れの中で仲間の身体を観察しながら、自分の身体の見られ方を学習することで、自分の客観的な姿のことを知っているため、鏡像と自分とを重ね合わせられるから。
(解答例2:視覚情報と体性感覚の結合をいれた)
チンパンジーは視覚の情報と身体の感覚を統合できることに加え、群れの仲間と互いの身体を観察し合う経験を通して自分の客観的な姿を学習しているから。
・表現力の問題として「自己から見た他者の身体」と「他者から見た自己の身体」を簡潔に言い換えることが難しいです。「自己」は「自分」に言い換えるとして、「他者」を「他人」と言い換えると、「チンパンジーなのに、他人でも良いのか?」となり困ります。私の工夫として、「仲間」表現して回避しました。また後半では「自分の身体の見られ方」と受け身の形にして「他者/他人」を使うことを回避しています。また、「客観的な姿」とすることでも回避しています。
・設問一と二と同様、「他者から見た自己の身体」を知っているから、「鏡像を自分だと気づける」というのが、やや論理の飛躍だと思い、「鏡像と自分とを重ね合わせられるから」というのを足しました。
解答例2では、前半に視覚情報と体性感覚の結合をいれたことで字数を圧迫されたので、後半を強引にでも字数削減せざるを得なくなり、解答例1とはかなり違う表現を用いることになりました。「自己から見た他者の身体」と「他者から見た自己の身体」という情報を入れるべきだと思いますが、入らないので「仲間と互いの身体を観察し合う」としてしまいました。また、「群れの中で育つ中で」という内容も、「群れの仲間と」として短くしてしまいました。説明不足かもしれません。
設問(四) 私たちの身体イメージには他者の眼差しが刻印されている

まずは傍線部を解釈しよう!
この問題だけ「どういうことか」の問題ですね。そこで、傍線部を見ていくことになりますが、「AにはBが刻印されている」というものであって、特段難しくありません。
Aは「私たちの身体イメージ」、Bは「他者の眼差し」ですが、どちらもそのまま答案に使えない言葉です。
身体イメージというのは、この本文だけで通用する特別な意味を持つ言葉ですから説明しなければならないし、「他者の眼差し」は比喩表現です。なお、「刻印」も比喩表現です。
この3つを言い換えていくのが、基本路線になります。
一番簡単なのは「刻印」ですね。これは「深く関係している」とか「強く影響されている」などと言い換えれば済みます。
Aの「私たちの身体イメージ」は本文の趣旨を踏まえなければならないので、追って解説。Bの「他者の眼差し」も都合により最後に説明した方が分かりやすいので、後で説明します。
文法や論理を追いかけよう!
では、A「私たちの身体イメージ」について追っていきましょう。
例のごとく、傍線部の前後を見ていくと、傍線部直前には「その意味で」、直後には「のである」があります。
「のである」はこの解説記事でも3回目ですね。筆者の田中先生の口癖(書き癖?)なのでしょうか。いずれにしろ、ヒントなのでもちろんチェック!くどいですが、「のである」の前文に注目しましょう。
「その意味で」というのは、頻繁に登場する表現ではないですが、論を少し発展させながら進めるというくらいに理解しておけばよいと思います。前後で方向性が大きく変わるような接続ではないでしょうから、前の部分も読みましょう。
ということで、傍線部の前を見てみると、「鏡像認知は、多感覚統合の課題ではなく、他者と共存することを学ぶ経験に他ならない」とあります。さらにもう一文前に戻ると、「自己の身体が、他者の眼から見てどう見えるのかに気づくことが必要」と書いてありますね。
そう、実はこれ、設問三の部分で解説したことと同じ内容が繰り返されているだけなんですね。
細かく言うと、設問三ではチンパンジーの話をしていましたが、チンパンジーの話はあくまで人間の赤ちゃんの鏡像認知を説明するための補助として引用しただけです。すぐに人間の話に戻って、同内容が繰り返されているのです。
そして傍線部エの辺りで文章が締められています。
ということは、設問三の部分あたりの内容を人間に当てはめればよいだけです。チンパンジーと同様、人間も他者から見られた自分の身体を学習するから鏡像認知が出来るようになるわけですね。
よって、A「私たちの身体イメージ」とは、人間が発達段階において、家族など他の人に囲まれながら、自分が他人からどう見られているのかを学習して形成されるイメージのことです。
「他者の眼差し」とは?
ではBの「他者の眼差し」についてですが、これは上で述べたように、赤ちゃんが成長しながら「身体イメージ」を形成する時に感じる、他人からの視線(ケアや保護なども含むでしょう)の事でしょう。
しかし、ここで気になるのは傍線部直前の「その意味で」と「刻印されている」です。
「その意味で」に関して、私は前の部分を少し発展させて論を展開させていると解釈しました。つまり、単に「他者から自分がどう見られているか」ということだけを言っているわけではないのではないか。
そしてわざわざ「刻印」という印象の強い言葉を用いている。
この2点から、私は単に見られているだけではなく、他人からの視線を気にしてしまっている自分や、もっと言えば他人の評価や印象に自分が左右されてしまっているのではないか、というところまで考えました。
考えすぎかもしれませんが、以下のように答案を作成してみました。
平井答案の解説
自分の身体を認識するには、視覚からの情報と身体の感覚とを結びつけるだけではなく、他人を観察しながら、他人からどう見られているかという点に気づくことが必要であるため、自分の姿に対する自覚には他人からの印象や評価が深く関わっているということ。
・この傍線部は鏡像認知の話ではなく、あくまで自分の身体のイメージの話だと思ったので、「鏡像」には触れていません。
・メインは「他人からどう見られているか」という部分ですが、「本文の趣旨を踏まえる」ということで「視覚情報と体性感覚の統合」の部分も入れました。
・「他者からの眼差し」は「他人からの印象や評価」とし、「刻印されている」は「深く関わっている」と言い換えました。
まとめ・講評
例年に比べて難易度は抑え目ですね。
論理の展開も明解で、文法的に考察できる部分も多く、要素を見つけるのもそれほど難しくはない、ということで、東大現代文の入門として非常に良いのではないかと思います。
一方で、熟練者であっても、論理を丁寧に繋いで記述するとか、日本語の表現をうまく選ぶとか、そういうレベルになると、ちゃんとある程度難しく、良い問題だなぁと思いました。
何かを批判するような内容でもなく、純粋に勉強になる面白い文章だということもあり、読んでいても心地よかったです。
【さらに深く学びたい方のために】
敬天塾では、さらに深く学びたい方、本格的に東大対策をしたい方のために、映像授業や、補足資料などをご購入いただけます。
ご興味頂いたかたは、以下のリンクからどうぞご利用下さい。
※なお、本稿では最低限の読解や私(平井)の答案の紹介を行っています。
《より詳細な内容》に加え、《多くのサンプル答案に対する添削やアドバイス》などを1時間半ほどかけて解説した授業動画もご用意しております。
ご自身でサンプル答案の添削に挑戦していただいた上で視聴いただくと、多くの気づきを得られます。

解説2025.jpg)