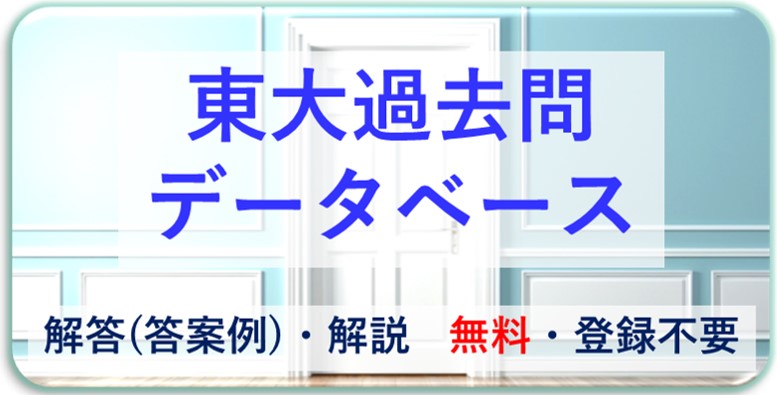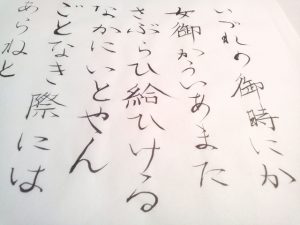2023年東大英語(第5問 物語読解)入試問題の解答(答案例)・解説
2023年東京大学 英語 第5問 物語読解
東京大学の第5問では、物語文(小説)の長文読解問題が基本的に出題されます。
現代文を思わせるような凝ったつくりの設問も散見され、文章自体にも面白さと難しさが混在した名文が多く見受けられます。
物語文の特性上、つかみどころがないと嘆く受験生も多くいますが、東京大学が第1問から第5問まで受験生に求めている能力がそれぞれ違っていることに気付くと、上達は早いと思います。
そして、東大物語文の設問を解くために留意すべき諸点を意識すれば、それほど恐れる相手でもなくなります。
物語文の出題割合は、年々下がっており、旧センター試験の問題からも平成後期になってあまり見られなくなりました。
神戸大学や関西大学など一部の大学では比較的多く出題されますが、他大学ではほとんど出されませんので、物語文に特化した参考書が次々と絶版となり、予備校の授業でも時折少し取り上げられる程度の扱いになっています。
この点、東大模試の過去問では物語文が毎回出題されていますから、河合東大OPや駿台東大実戦や代ゼミ東大プレの問題集を日々のトレーニングに使うのも悪くはありません。
ですが、やはり、過去問が最高かつ最強の学習ツールであることには変わりありません。その理由をいくつか挙げます。
東大過去問の物語文には
- 桁違いの面白さやひねりがある(読み終わった後も不思議な感覚に駆られることが多く、まさに小説という感じ)
- 受験生のレベルに合わせてリライト(書き直し)が適宜なされており、いたずらに難しい語彙や語法で受験生を惑わすような東大模試とは一線を画する。計算づくで作られており、練りにねった名問も多く、予備校講師をあっと言わせるものばかり。
- 中学受験や高校受験でよく出るテーマ(離婚・離別・いじめ・青春など)のようにテンプレ化された内容ではない。
といった特徴があります。
東大型の模試をつくったことがありますが、作問者の視点から見ても、東京大学の問題は本当に面白く、難しくもあり、計算づくで作られていることがわかります。
いくら出題形式を真似ても、コピーは決してオリジナルには勝てないことが、よくわかりました。
それもそのはず、半永久的に、様々な受験生や教育関係者達に見られ続ける東大の入試問題を作るわけですから、東大教授陣に課されたプレッシャーは半端ないものです。
最高学府の威信をかけてつくった問題と、1〜3年しか注目されない予備校の問題が同次元なわけがありません。
理数系科目では、模試にも良問が時たま見られますが、文系科目では違う世界の言語ではないかと思うくらい、クオリティが異なります。
それゆえ、東大文系科目は東大過去問でしか対策が取れないと、私は考えています。
話を戻しましょう。
この第5問ですが、2022年度入試においてはLGBT、2023年度入試では刑務所廃止論をテーマとした文章が出題されました。まさに旬の話題です。2022年11月には東大駒場キャンパスで1〜2年生が学ぶ英語テキストが10年ぶりに刷新されましたが、こちらの書籍を監修された田尻教授の寄稿文だけでもご一読いただくと学びがあるかもしれません。
https://park.itc.u-tokyo.ac.jp/eigo/publication8.html
さて、上で東大第5問には面白さやひねりがあると申し上げましたが、論より証拠、ぜひ過去問を探究してみましょう。
単調なストーリー展開でないことは、母と娘の確執をテーマとした2015年の東大第5問などをご覧いただければ、すぐわかると思います。読了後も不思議な余韻が残ります。
ちなみに、「親子の想いの違い」は東大では比較的よく出されます。
面白いストーリー展開ということでは、以下の2つは特に外せません(笑)。
2000年 家に帰ってきたら、知らないロシア人が料理をつくっていた ← ホラーですよね(笑)
1993年 道端の溝に、不思議な帽子を被ったおじさんがハマっていた。←シュールな話ですよね(笑)
その他にも、しんみりする話や、滑稽な話、神秘的な話や共感する話など、まさにこれぞ小説の醍醐味といった作品が数多く登場します。80年代や90年代の過去問でも十分にお楽しみいただけると思います。
ちなみに開成や筑駒など東大に毎年多数進学する高校の生徒達だけが主に通う鉄緑会さんでは、1978年以降の東大過去問を受講生に配布しているようですが、さすがです。
ただ、こちらをお持ちでなくとも、以下のサイトなどで70年代からの過去問がアップされていますので、ぜひお楽しみください。受験学年でない方も少しずつトライしてみましょう。東大第5問の魅力の虜になるかもしれませんよ!
東大第5問制覇のコツを知り、作品自体も楽しめるようになると、今年はどんな問題が出るんだろうとワクワクした気持ちで東大入試に臨むこともできるでしょう。
なお、第5問には客観式問題が多く散りばめられており、高得点合格者は総じてここで点数を奪取しています。
2021年度のデータにはなりますが、以下の分析表をご覧ください。

いかがでしょうか。第5問の正答率が極めて高いですね。
もちろん、87点の方は半分しか取れていませんし、人それぞれの得点戦略はありますが、できれば第5問でもガッツリ点数を取りたいものです。
客観式問題は、一意的に答えが定まるものですし、減点を食らうリスクもありません。
客観式問題で高得点を取りつつ、そこに記述問題での得点を上乗せしていくイメージで学習戦略を構築していきましょう!
なお、第5問には記述式問題もあります。東大模試とは異なり、やけに解答欄が大きく、そんなに書くことがないのにどうしようと試験会場で動揺される方がそこそこいると聞きます。
敬天塾なら、どのような答案を書くか、サンプルを示したいと思いますのでご参照いただけると幸いです。
(解答例)
(A) problems by repeating the kind of behavior that brought us
(B) 子どもたちは、スペインでは殺人罪の平均刑期がたった7年であるということを聞き、その事実に対して強い憤りを覚えたため、刑務所を廃止すべきだというギルモアの考えに対して当初抱いていた怒りがほんの少し和らいだ。
(C) 子どもたちは他の場所で起こったことは自分たちの生活には関係ないと判断し、ギルモアが伝えようとしたことを気にも留めないだろうと予想していたから。
(D) (ア)(26) d (27) f (28) a (29) c (30) e (31) b
(イ) c
(ウ) c
なお、この第5問に関して、2022年度の作問担当 東大教授からのメッセージを最後にお伝えしたいと思います。
(東大教授からのメッセージ)
文章全体の流れを大局的に把握しながら、文章の細部に含まれる表現のニュアンスをも同時に読み取れるような総合的な理解力が求められています。より具体的には、文章に書かれた出来事や事象がどのような経緯をたどって生起しているのかを正確に把握しつつ、細部の表現に込められた書き手や登場人物の心情や価値観、ものの見方などを的確に理解することが重要です。
第5問を早期に完成させ、ゆとりを持って東大英語を制覇しましょう!
【さらに深く学びたい方のために】
敬天塾では、さらに深く学ばれたい方、本格的に東大対策をしたい方のために、映像授業や、補足資料などをご購入いただけます。
東大第5問小説の訓練方法や、頻出の多義語習得のコツなどにご興味のある方は、以下のリンクからぜひ合格エッセンスを貪欲に学ばれてください。
漫然と問題を解くだけでは気付きにくいコツや、東大第5問のネタ本とされている書籍の情報などもお伝えしています。
映像授業【東大英語 第5問 エッセイ(物語読解)】
過去問に対して、これでもかと噛み砕いて説明した《実況中継》の解説もございます。
↑ まずは目次と無料部分だけでもどうぞ。
東大模試で出てくるような難解な単語が出されない反面、多義語の力や語法の力が試されています。
語彙力強化講座も併せてご検討ください。
映像授業【東大英語 語彙力強化(英単語暗記)】基本動詞・多義語の底力!灘・筑駒・開成生も絶賛!