2023年東大英語(第2問B 和文英訳)入試問題の解答(答案例)・解説
目次
2023年東京大学 英語 第2問B 和文英訳
(編集部注)難易度の評価など、当日解いた所感はこちらをご覧ください。
問題
なぜ歴史を学ぶようになったのか、理由はいろいろあるのだが, いまの自分たちの住む世界について, それがどのように出来上がってきたのか, なぜいまのような形になったのか,ということにぼんやりとした関心があったことは確かだろう。さらにもう少し掘り下げてみると, 日本の近代化がヨーロッパの影響を受けながら辿ってきた道筋を考えるには, そのヨーロッパのことをもっと知らなければならない,といったことも感じていたのだった。 高校時代はアメリカにあこがれていた。 当時流行っていたフォークソングに惹かれていたし, 西部劇や東部の有名大学の学生たちのファッションにも夢中になっていた。 それが大学に入ってからヨーロッパ, 最初はドイツ, やがて英国に関心が移っていったのは自分でもはっきりと説明することは出来ない。
(草光俊雄 『歴史の工房 英国で学んだこと』)
総括
2018年に20年ぶりに復活した和文英訳問題ですが、本年度も2Bで登場しました。
皆さんは、和文英訳と聞いた時に、どのようなスキルが求められるとお考えですか。
思考プロセス
問題文を再掲します。
なぜ歴史を学ぶようになったのか、理由はいろいろあるのだが, いまの自分たちの住む世界について, それがどのように出来上がってきたのか, なぜいまのような形になったのか,ということにぼんやりとした関心があったことは確かだろう。さらにもう少し掘り下げてみると, 日本の近代化がヨーロッパの影響を受けながら辿ってきた道筋を考えるには, そのヨーロッパのことをもっと知らなければならない,といったことも感じていたのだった。 高校時代はアメリカにあこがれていた。 当時流行っていたフォークソングに惹かれていたし, 西部劇や東部の有名大学の学生たちのファッションにも夢中になっていた。 それが大学に入ってからヨーロッパ, 最初はドイツ, やがて英国に関心が移っていったのは自分でもはっきりと説明することは出来ない。
(草光俊雄 『歴史の工房 英国で学んだこと』)
下線部を句読点ごとに区切ってみますと、4つのパートに分かれます。
① さらにもう少し掘り下げてみると
② 日本の近代化がヨーロッパの影響を受けながら辿ってきた道筋を考えるには
③ そのヨーロッパのことをもっと知らなければならない
④ といったことも感じていたのだった。
とあります。
多くの受験生は下線部だけ読んで英訳を試みるわけですが、なぜに東大側が下線部前後の文章を載せているのか考えてみてください。
それは、訳しづらい箇所が出てきた時にヒントにして欲しいという思いを込めているからです。
4A正誤でも、4B英文和訳でも、5の物語文でも下線の所だけ拾い読みする受験生が多くいますが、東大教授も作問にあたり、そうした受験生の存在を想定してワナを仕掛けています。
2Bについては、確かに下線部だけ読めば何とかなることも多いのですが、2020年2Bの「まゆつばもの」のように、下線部以外のワードから適切な訳語を類推しなければならない設問も出されますので、臨機応変に問題文を活用しましょう。
なお、東大や京大の2Bでは堅い文体で人生訓などありがたいお話がよく出されますので、文意を正確に把握するためにも日本語の語彙力を磨くことも忘れないようにしましょう。
東大入試では、全教科的に国語力が高度に求められているからです。
また、人生訓の英訳訓練を京大や阪大あたりの過去問も使いながら訓練しましょう。それでは、①〜の順に見て行くとします。
「① さらにもう少し掘り下げてみると」の英訳を泥くさく考察してみた
英語の知識が豊富にある方なら、「掘り下げる」の訳語として、delveやdigという訳語が思いつくかもしれません。
ですが、大多数の受験生は、delveなんて聞いたことないだろうし、「掘る」という日本語を逐語訳したdigなんて使えるのだろうかと試験会場で思われるはずです。
では、試験会場で気づける合格者の思考プロセスはなんでしょうか。
まず、課題文における下線部の位置に着目すると、文章の中盤に書かれており、その直前では、「なぜ歴史を学ぶようになったのか」を筆者が色々と考察している様が書かれています。
それを受けて、「さらにもう少し掘り下げてみると」と言っているわけです。
であるなら、「より深く分析してみると」と言い換えてanalyze the reason moreということも出来そうです。
でも、これでは、まだシンプルとは言えなさそうです。
ここで、「さらにもう少し掘り下げてみると」を5歳児にもわかるように言い換えてみましょう。
小さな子供に、「掘り下げる」なんて言葉を使ってもわからないしょうし、掘ると言われても土を掘るくらいしかイメージがわかないはずです。
ここでの「掘る」の目的語は、自分の考えをより深く掘り起こすことを意味しているのでしょうから、「より深く考える」と捉えてthink deeplyとすることも出来そうです。
でも、せっかくですから、ここで満足することなく、もう少し欲張ってみましょう。
「さらにもう少し掘り下げてみると」という一節に深い意味はありますでしょうか。
ハッキリ言って、何の情報価値もありませんし、強いて言うなら、「付け加えて」いるだけですよね。
であるならば、In additionやFurthermoreといった高1でも知っているシンプルな表現で表しても十分のように思えます。
以上の考察をまとめてみます。
(試験会場で書きやすい超絶シンプルな表現)
In addition,
Furthermore,
Moreover,
といった情報追加の機能を持つ副詞
(ちょっと工夫が必要な表現)
think deeply
→実際に答案に書く時には、目的語を明示したいのでthink about the reason(itで受けてもOK) more deeplyにした方が良いでしょうし、後続の文との関係を考えるなら、分詞構文にしてthinking more deeply about the reasons やthinking deeply about itにしたり、If節を繋ぎ役にしてIf I think more deeply about the reason、あるいはもっとシンプルにwhen I think deeply about itなどとすることもできますが、ちょっと処理量が増えてしまうのがネックです。
分詞構文を利用して敢えて目的語を示さずThinking deeplyだけで書くことも出来なくはないと思います。
また、そもそもdeeplyという副詞が思いつかない場合は、シンプルにmoreだけでも良いと思います。
もちろん、deeplyやらdeepが思いつけばコロケーション的にも良いのですが、試験会場でパニックを起こしている時に何も思いつかないのであれば、中学レベルの英単語を組み合わせてみたり、下線部を思いっきり意訳して、もっとも主張したい「核」のところだけ端的かつ明瞭に書いて1点でも多く稼ぐスタンスは重要です。
(本番で気づくことは難しいが、こんなの書けたらイイネという表現)
When I delve a little deeper
If I dig into the reasons a little more
Digging a little deeper
when I dug deeper into it
On deeper reflection
いかがでしたでしょうか。
模範答案を眺めて「すごいね!こんなの書けたらいいね!」という感想だけで終わっていた方は、ぜひ、頭の中に入っている知識を駆使できるように、与えられた日本語文を英訳しやすいように別の日本語に言い換える和作文を実践してください。
今回の「さらにもう少し掘り下げてみる」であれば、
「もう少し深く考えてみると」
「もっと分析してみると」
「さらには」といった具合に、
どんどんパラフレーズ(言い換え)してみましょう。
言い換えに際しては、小難しく考えるのではなく、5歳児に説明するくらいの気持ちで、日本語の語彙レベルを落として言い換えてみると良いでしょう。
我々の脳内にストックされている日本語の語彙数に比べ、英語の語彙数は微々たるものなわけですから、ストレートに英訳できないことは多々あります。
そうした問題を解決するのが、与えられた日本語文を英訳しやすいように加工する技術なのです。
和文英訳というと、日本語→英語にダイレクトに訳されることをイメージされる方が多いと思いますが、日本語→日本語→英語というプロセスを経ることで難易度の高い英文にも怖気つくことなく冷静に英訳を試みる勇気が芽生えてきます。
この手法は、第一線でご活躍されている翻訳家や同時通訳者の方も多用されているようです。ぜひお試しください。
「② 日本の近代化がヨーロッパの影響を受けながら辿ってきた道筋を考えるには」の英訳を泥くさく考察してみた
こちらのページでは省略しております。映像授業【東大英語第2問B 和文英訳】に入れております。
「③ そのヨーロッパのことをもっと知らなければならない」の英訳を泥くさく考察してみた
こちらのページでは省略しております。映像授業【東大英語第2問B 和文英訳】に入れております。
「④ といったことも感じていたのだった」の英訳を泥くさく考察してみた
こちらのページでは省略しております。映像授業【東大英語第2問B 和文英訳】に入れております。
さて、以上のように4つのパートに分けて分析考察してきたわけですが、各パートの表現を組み合わせれば答案骨格は出来上がります。
その上で、英作文における7つの大罪でもお伝えしたように、時制や三単現のsなどに注意して、スペルミスやピリオドつけ忘れといった初歩的なミスを犯さないように最後の仕上げをしていきましょう。
最後まで油断しないことが合格ポイントです!
さて、ここで、いくつかの答案例を示したいと思います。
これなら私にも書けるかもと思わせてくれる答案例
① In addition, I also felt that I had to learn more about Europe in order to think about how Europe helped Japan modernize.
② When I thought deeply, I realized I had to know Europe more to understand Japanese modernization which was influenced by Europe.
③ Furthermore, I also realized that I needed to know about Europe so that I could understand how Europe had an impact on Japan’s modernization.
④ In addition, I felt that I had to have more knowledge about Europe in order to think about the process of modernization in Japan which was influenced by Europe.
⑤ Moreover, I also felt that in order to understand the way Japan developed owing to Europe, I had to learn about it more.
こんなのを書いてみたいと思わせてくれる答案例
① When I delved a little deeper, I also felt that I should know more about Europe to better understand how Japan had achieved modernization under the influence of Europe.
② On deeper reflection, I also realized keenly that in order to understand how Japan modernized under the influence of Europe, I needed to learn more about it.
【さらに深く学びたい方のために】
敬天塾では、さらに深く学びたい方、本格的に東大対策をしたい方のために、映像授業や、補足資料などをご購入いただけます。
ご興味頂いたかたは、以下のリンクからどうぞご利用下さい。
映像授業【東大英語第2問B 和文英訳】
過去問に対して、これでもかと噛み砕いて説明した《実況中継》の解説もございます。
↑ まずは目次と無料部分だけでもどうぞ。

解説2023.jpg)
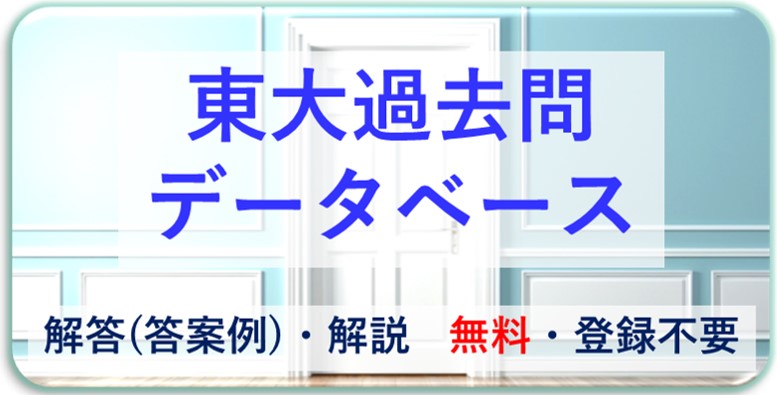


解説2023-300x161.jpg)