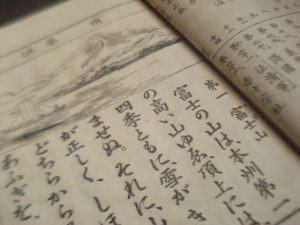国語10月②2014年第4問
こんにちは、スタッフAです。
今回はついに第4問を扱いました。内容が難しく、設問が少ないのが第4問の特徴です。
様々な解釈があると考えられますが、授業内に出た指摘や表現の違いをまとめました。
2014年第4問
(一)
「ずぶりと差しこまれる」をどう表現するのか、とても悩む問題でした。
以下は、生徒の答案の中から抜き出しています。
平凡さを切り拓く衝撃がある
唐突に訪れ
驚き
鮮烈な刺激
否応なく訪れる
突然日常に現れた未知の事柄
不可避な違和感
自分で答案を作成してから出ないと、差異や良さに気づくことは難しいと思います。ぜひ、この問題の答案を作成してから読んでください。
なお、ぼくは、答案の中で「作者」という言葉を使いましたが、「筆者」のほうが良いそうです。今日も勉強になりました。
(ニ)
松ぼっくりや新たなページの取扱いがで意見が分かれました。初めに本について書き、その後に植物園について触れると標準的で見やすい答案となるようです。もちろん、異なる構成であっても、問題ありません。こんな意見もありました。
松ぼっくりは例であって、使用するならば例であることを示す必要がある。
字数に余裕があるならば「大きな松ぼっくりのような、普段出会わない現象」といったように、松ぼっくりとそれを抽象化した表現の両方を書くと良い。
この問の答案を生徒はこんなふうにまとめています。
未知の世界へ誘うということ
新たな発見が転がっているということ
未知の世界を知ることができるということ
未知の情報や体験との出会いとなる
いつもと違った発見をすることができるということ
新たな発見を楽しむことができるということ
新たな発見が得られるということ
普段恵まれない有意義な邂逅に与れること
(三)
とくに難解な問題だったと思います。「一歩」については、生徒の解釈は概ね同じ方向を向いていたと感じました。しかし「消えていく光」は何を指しているのでしょうか。筆者にしか分からないことですが、自分なりに解釈してまとめなければいけません。
生徒の答案の文末は以下のとおりです。
明確な答えが出ずかえって正体が分からなくなる気になるということ
正体を知ることもできずに忘れ去られるということ
確かめようとしたものが結局なんだったのかわからないまま失われていくということ
新たな曖昧さや疑問を生み出す素となる
途方に暮れる絶望感に苛まれるということ
未知性という魅力が失われてしまうということ
また新たに疑問を生むだけだということ
曖昧さは変わらないということ
狐につままれた感覚に陥ること
(四)
様々な解釈の答案がありましたが、個人的には、松ぼっくりや馬の歯を持っている人が何を考えているかは分からず、筆者が想像で勝手に詩を感じたと読み取りました。そのため、筆者以外の人の感情や意図には踏み込むべきではないと考えます。
一番良いと思った答案は、
「他者にとって、未知のことに関心や知識を持ち、明確な答えのない疑問とそれに導かれる想像の世界へ、詩のように他者を誘うことのできる話を持つ人がいるということ」
です。読みやすく、過不足もなく、問いに対し正面から答えている答案であると感じました。
第4問は、いつも以上に本文の読み込みが重要だと感じました。
次回も、第4問です。