2022年東大英語(第4問A 英文法正誤)入試問題の解答(答案例)・解説
4A正誤問題に関しては、捨て問にする受験生も多いと思います。
ですが、以下の表をご覧いただければわかるように、2021年東京大学合格者の再現答案を分析すると、
80点を超える開示得点の合格者は総じて4Aでガッツリ点を取っていることに気付かされます。
もちろん、多くの受験生にとって優先度が低い問題かもしれませんが、2問くらいは取っておきたい問題でもあります。
とはいえ、私大の正誤問題のように短い文章がサラッと出されるのとは異なり、設問文の長さが年々増加しており、もはや長文読解のようにもなっています。
東大が重視するTOEFLで文法パートが廃止されたことから、4A正誤問題がいつ消えてもおかしくはないと私は考えていますが、東京大学の学内報を見る限り、正確な文法力や正確な語法力に基づいた訳読を重視するスタンスは教授陣の中にあるようですので、4B英文和訳と合わせて、今後も出題されることでしょう。
さて、2022年度の4A正誤問題ですが、上述した通り、長文量がここ数年では一番多くなっています。
ご参考まで、2019年以降の語数をあげますと、
2019年 561 words
2020年 518words
2021年 464words
2022年 589words
となっています。ただ、慶應や上智の長文量に比べれば、そこまで多くはありませんから、これくらいは処理してほしいなという思いもあります。
東大英語が事務処理能力テストであることは公知の事実なわけですから、大問別のトレーニングをしっかり実践できた方には、十分に対処できる量だと思います。
なお、難易度については、難しい選択肢もありましたが(23)や(25)あたりは取りやすい問題でもありましたので、ここで4点をもぎ取って欲しかったなと思います。
その他、4A関係で重要なのは、何番目に解くかです。
合格者にアンケートを取ると、たいていは一番最後に解くことが多いですが、中にはリスニングの直前に解く方もいました。
各大問をどの順番で解くのか、リスニングの前に解くのか後に解くのかについては、東大英語を処理する上で極めて重要な視点ですので、各々に相応しい戦略案を考えましょう。
さて、話を戻すと、東大4A正誤問題はここ10年のうちでも、形式が目まぐるしく変わっています。
私大であれば、細かな文法と語法を問うてきますが、東京大学では更に文脈上不適切なものを選ばせてもいます。
これが意味することは、下手なテクニックは通用しないということでもあります。
求められる力も少しずつ変わってきています。
東大英語はリスニングや英作文を筆頭に年々進化してきていますので、早期に適切な大問別トレーニングを行うことが重要です。
目次
設問(21)文意(語法)本年度の4A最難関の設問がいきなり!?
誤った選択肢は(c)
A government that generates a disaster like this may have (b)some chance of escaping public anger if the news of (c)it is to be削除 effectively suppressed, so that it doesn’t have to face criticism of its policy failure.
本問は、2022年度4Aで最も難しい設問であった。
一読したときに、明らかな間違いが見つけられなかった一問である。
だが、下線(c)には「こんな構文あったっけ?」と強烈な違和感を覚えたことは間違いない。
まず、下線(c)を含んだ一文を精査してみるとしよう。
すると、この下線部(c)はif節の中に入っていることがわかる。
ifとbe to構文がセットで出てくるフレーズと言えば、教科書レベルでは「if it were to〜」で始まる、話者が実際に起こりえないと考える未来の想定で用いる構文くらいではないだろうか。
当然、if内が現実に起こりえない話をしているのだから、帰結節(if節に対する主節のこと)も現実的に起こりえないと話者が考える話が書かれているはずだ。
さて、話を下線部(c)に移すとしよう。
仮に[if it were to]構文を用いようとしているのなら、be to構文がwere toになっていないことにも違和感を覚える。
また、帰結節の主たる動詞ががmay haveとなっていることからもif it were to構文の話ではないと判断した。
となると、このto beはいったい何のためにあるのだろうかと疑問に思った。
モヤモヤした気持ちを抱えながら、敢えて視点を変えて他の下線部を確認することにした。
下線部(e)では意味深にbeが書かれていて、ここに食いついた受験生ももしかしたらいたかもしれない。
だが、demandやrequireやinsistやsuggestといった要求提案系の動詞のあとのthat節には、見えないshouldの効力が働き動詞が必ず原形になるということは教科書レベルの知識である。
TOEICなどでも頻出であり、天下の東大受験生がこんなところで引っ掛かってはいけない。
下線部(a)や(b)も特に下線部(c)で感じたような謎の違和感を覚えない。
消去法からみてもやはり、下線部(c)なのだ。
私が受験生なら、このモヤモヤした直感を信じて選択肢(c)を選んだことだろう。
もう少し詳しく説明するなら、このbe to構文を入れることでいったい何を表現できているのかが文脈上理解できなかったのである。
つまり余事記載と言え、削除をした。
こうした余事記載パターンは、余計な前置詞を付け足して自動詞/他動詞の判別が出来ているかを試す設問(たとえば、2021年設問(25)、2017年(21)など)で散見されるが、今回のようなbe to構文の余計な付け足しパターンは記憶の限り東大4Aでは初めてのことのように思われる。
なお、本文全体を熟読すべきかは人により判断が分かれるところではあるが、少なくとも下線を含む一文はちゃんと読むべきであろう。
殊に、2022年4Aの長文は、おそらくこの年の英語長文の中で最も読みづらい部類の文章だった。
このレベルの文章をすらすら読める受験生にとっては、1Bや4Bや5の長文は赤子の手をひねるくらい簡単に思われたであろう。
逆に、1Bや4Bや5の長文で苦戦したり共通テストの英語R程度の長文で手こずったりする受験生は4Aの長文すべてを読み込むよりも、下線部における目の付け所を学んでサクッと解答することを心がけた方が残り時間や他教科とのバランスを考えた時に現実的かもしれない。
以上、ざっと書いてみたが、この空所(21)は、2022年度の4Aの中では、最も気付きづらい選択肢であったため、本番で出くわした場合、一旦、別の選択肢を先に吟味する駆け引きも重要である。
冷静さを維持できた人が、東大英語で勝利できることを肝に銘じなければならない。
ちなみに、2023年4A(21)も難易度が高かった。
最初の設問に難問を投下して受験生の冷静な思考を奪おうとするのが、近年の東大英語部会の戦略なのかもしれない。
やはり、こうした時ほど、冷静に、取れる問題から、キッチリ得点していくことを心がけたい。時間制約の厳しい東大英語だからこそ、「1分で1点を稼ぐ」スタンスを貫かれたい。
設問(22)前置詞 ちょっといやらしい問題だけれども、意外に正答率は高い!
誤った選択肢は(e)
Though, incidentally, are not Mill’s exact words, but those of Walter Bagehot ー though Mill (e)had made→done the done most for the idea to be understood.
詳細はこちらのページでは省略しております。映像授業【東大英語第4問A 英文法正誤】に入れております。
設問(23)名詞 これは瞬殺で正誤判断して欲しかった! 典型パターンです!
誤った選択肢は(b)
Public reasoning in pursuit of better decision-making (a)has been used not just in the post-Enlightenment Western world, but (b)in other societies and at other time→times, too.
設問(24)動詞(語法) これもサービス問題! 見落としてはいけない1問です!
The idea that democracy is ‘government by discussion’ーand not just about votingー(d)remains as削除 extremely relevant today.
詳細はこちらのページでは省略しております。映像授業【東大英語第4問A 英文法正誤】に入れております。
設問(25)動詞(時制)
誤った選択肢は(a)
(a)I was→have been interested in this question since my schooldays when my grandfather Kshiu Mohan drew my attention to Emperor Ashoka’s rulings on public arguments, but Mill and Keynes offered me a new understanding about the role of public discussion in social choice.
詳細はこちらのページでは省略しております。映像授業【東大英語第4問A 英文法正誤】に入れております。
東大4Aは、コツをつかめば、ほんのちょっとの労力で3問は確実に正解できる「おいしい」問題です。
今年度の問題で言えば、(23)(24)(25)は瞬時に気づいて欲しかった設問でした。
ぜひ、過去問探究や敬天塾の映像授業などを通じて、ノウハウを学び取っていただき、東大英語で高得点を奪取していただければ、この上ない幸せです。
【さらに深く学びたい方のために】
敬天塾では、さらに深く学びたい方、本格的に東大対策をしたい方のために、映像授業や、補足資料などをご購入いただけます。
ご興味頂いたかたは、以下のリンクからどうぞご利用下さい。
映像授業【東大英語 第4問A 英文法正誤】
過去問に対して、これでもかと噛み砕いて説明した《実況中継》の解説もございます。
↑ まずは目次と無料部分だけでもどうぞ。

解説2022.jpg)
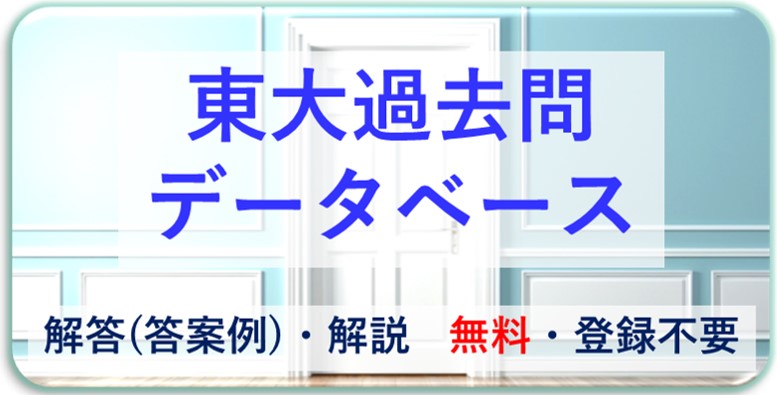



解説2022-300x161.jpg)