2025年東大英語(第4問B 英文和訳)入試問題の解答(答案例)・解説
(編集部注1)難易度の評価など、当日解いた所感はこちらをご覧ください。
(編集部注2)実際の入試問題入手先
本解説記事を読むにあたって、事前に入試問題を入手なさることを推奨します。
・産経新聞解答速報 https://www.sankei.com/article/20250225-SS6KISNKS5BRTKNOCIBINS4GHI/?outputType=theme_nyushi
・東京大学HP https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/admissions/undergraduate/e01_04.html
目次
- 【2025年東京大学 英語4B 英文和訳総括】おや?模試の時のように下線部だけ読んでも上手く訳せないぞ?
- 東大英語4B英文和訳 2020〜2025分析シート
- 【下線部(ア)の和訳ポイントと和訳の工夫】 “You can’t say that!”って何?言っちゃいけないことって何なのか明示されておらず動揺する受験生が続出!
- 下線部(ア)の解答例
- 2025年度4B(ア)を解くために下線部以外も読んでおくべきだったか
- 【下線部(イ)の和訳ポイントと和訳の工夫】それほど難しい構文や単語は使われていないのに、なぜかしっくり訳せない。これぞ、まさに東大4B!
- 下線部(イ)の解答例
- 2025年度4B(イ)を解くために下線部以外も読んでおくべきだったか
- 【下線部(ウ)の和訳ポイントと和訳の工夫】本問については下線部だけで真意を掴めた人もいたかもしれませんが、多くの受験生には難しかったのでは?
- 下線部(ウ)の解答例
- 2025年度4B(ウ)を解くために下線部以外も読んでおくべきだったか
- (雑感)
- 【さらに深く学びたい方のために】
【2025年東京大学 英語4B 英文和訳総括】おや?模試の時のように下線部だけ読んでも上手く訳せないぞ?
2025年度入試の4B英文和訳で、手こずった受験生は多くいたことでしょう。
世間では、かなり話題になりました。
「英文和訳の集大成とも言える問題だ」
「ちょっと構文解釈の勉強をしたからと言って、4Bを得点源にできると思うなよって言われている気がする」
「何のために下線部以外の英文があるのか、ちゃんと考えろよってことか」
「東京大学さまが本気を出してきた」などなど、SNS上でも様々な声が聞かれました。
少し前までは、下線部だけを読めば答えがわかる和訳問題が出されることも多かったので、面食らった受験生が続出したようです。
では、なぜに手こずったのかというと、問題と向き合う姿勢を東大側に強く咎められたためです。
皆さんがもしも、「東大英語は1Aや4Bが簡単だからサクッと終わらせよう」という指導を受けているのだとしたら、それは平成時代の話ですので、そうした考えは今すぐ捨ててください。
今年の1Aは昨年よりマイルドにはなりましたが、ここ数年、東大側は各大問でちょこちょこ出題傾向を変えてきています。
問題形式の見た目はこれまでと変わっていないように見えて、設問のつくり(中身)が変わってきているのです。
今年の4Bに限って言えば、下線部(イ)のinsidersという基本単語は知っていても、下線部だけ拾い読みした人には、「え?どういうこと?」と動揺したでしょうし、
下線部(ウ)のridに至っては聞いたことすらない受験生がほとんどだったと思います。
文脈をちゃんと追わないと正確には訳せないよう、東大教授は計算づくで作問しているのです。
ご存知のように東大英語は日本一時間制約の厳しい英語試験と言ってもよく、受験生は少しでも短時間で問題処理をしようと試みます。
その結果、4B英文和訳であれば、本文をたいして読まずに下線部だけ読んでも、ちゃちゃっと和訳しようとします。
読解総語数を減らすことで、時間を節約し、省エネしようとしているわけですね。
ですが、ここ数年、東大英語試験問題作成部会は、そうした受験生の態度を咎め、本文全体をちゃんと読め!と強いメッセージを送り続けています。
本年度の4Bで手こずった方は、ぜひ本解説を通じて、東大教授の想いを汲み取ってください。
なお、4B英文和訳を解くに際しての諸原則や出題傾向につきましては、映像授業でも詳述しておりますので、あわせてご参照ください。
東大英語4B英文和訳 2020〜2025分析シート

いかがでしょうか。これを見る限り、長文語数はここ20年で増加傾向にありますが、下線部語数自体はそれほど大きく変わっていないようにも思えます。
ただ、見かけ上の語数からだけでは、正確な難易度比較はできませんので、必ず過去問で問題文と実際に対峙して、東大教授がどのようなチカラを受験生に求めているのか感じ取るようにしましょう。
それでは、早速、2025東大4B英文和訳について解説をしていきたいと思います。
【下線部(ア)の和訳ポイントと和訳の工夫】 “You can’t say that!”って何?言っちゃいけないことって何なのか明示されておらず動揺する受験生が続出!
構文レベル★★☆
語彙レベル★☆☆
訳出工夫度★★☆
(ア)“You can’t say that!” I imagine someone sitting around an evening fire suddenly shouting to the community’s favorite storyteller.
この4Bの最初の設問が本問となります。
本問に関しては、[sitting around an evening fire]と[shouting to the community’s favorite storyteller]の部分が、共にsomeoneにかかっている文構造を理解できれば難なく訳出はできたでしょう。
ただ、本問のイヤラシイところは、You can’t say that!(そんなこと言ったらダメだ!)の「that」の内容が本文のどこにも書かれていないことにあります。
下線部(ア)の直前にCensorship may be as old as literature itself(検閲は文学と同じくらい古くからある)という文が書かれていますが、これを指していると思い込んでしまうと、途端に第1段落の内容が掴めなくなってしまいます。
ネタバレすると、この第1段落第1文のCensorshipの内容は、全文を通して読むなかで、徐々にその意味が見えてくるものです(いま風に言えば解像度が上がってくる)。
ですので、下線部(ア)の内容を完璧に理解しようとして、第1段落だけを隈なく読んだところで、要旨をうまくつかむことはできません。
さらには、下線部の「I」は、焚き火を囲んでいる人ではなく、現代の人です。現代の人が、昔の人はこんなことをしていたんだろうなと思いを馳せているからこそimagineを用いているのです。
焚き火の前に座っている人も1人ではないでしょう。
それは下線部(ア)のあとで、calls out anotherやらthe next gatheringとあることからも、複数人いたと言えます。
そもそも、語り部は複数の人々に物語を語る人なのですから、目の前に1人しかいないというのは考えにくいというのもあります。
とはいえ、本年度の4Bでは「that」の指す内容を説明せよといった条件が付されているわけではなく、ただ単に「和訳せよ」としか指定されていませんので、本問に関しては淡々と逐語訳すれば十分だったとも言えましょう。
もちろん、文脈全体を把握して、焚き火のまわりでstoryteller(語り手)が皆に話をしている場面を想起できると、ストーリー展開が頭に入ってきやすくなるのは事実です。
昨年度の4Bでも、情景をイメージできると和訳しやすかったと思いますので、東大英語部会が意図的にそうした文章をチョイスしてきていることは明らかです。
以上の内容をもとに和訳作業に取りかかります。
その際に注意すべきことは、2023年度4B実況中継解説でも詳述した通り、英文和訳は逐語訳が鉄則であり、訳していくなかで日本語として不明瞭な箇所を文構造を崩さずに部分的に意訳していくことが合格ポイントです。
雰囲気で訳そうとすると、構文がわかっていないから誤魔化したんじゃないかと採点官に疑われます。
こなれた日本語にするにしても、構文をわかっていますよアピールはしなければいけません。
まず、”You can’t say that!”については悩む要素はないでしょう。
thatの内容を書けとは言われていませんから、シンプルに「そんなことを言ってはいけない」とでも訳せばOKです。
ただ、この”You can’t say that”がshoutingの目的語になっていることに気づきましたか?
私はそのことに気付いていますよと、採点官にアピールせねばなりません。
そして、一番の問題は、その後の文です。
大枠としては、imagine 人〜ing(人が〜をしているのを想像する)なのですが、〜ingが2つ来ているので動揺した受験生もいたかもしれませんが、
後半のshouting〜がfireを修飾していると考えるのは意味的に無理がありますから(火が叫んでいるというのはファンタジーにも程があります)、
ここは素直にimagine ■ shouting〜と捉え、■の中身がsomeone(sitting around an evening fire)だと考えるのが自然です。
訳出で苦戦するような単語はないとは思いますが、強いて言うならstorytellerとcommunityでしょうか。
まずstorytellerについては、storyをtellする人(er)と、そのまんまの意味となります。
これを「語り手」「語り部」といった小慣れた日本語に訳せなかった受験生は一定数いたと思います。
ですが、意味が伝われば十分なので「物語を伝承する人」「物語をみんなに話す人」と訳しても良いかもしれません。
なぜ、「物語」という言葉が出ていたかというと、第1段落の最後に、modifies the taleとありますから、the tale(物語)を伝える人のことをstorytellerは指しているんだろうなと推測できるからです。
次に、communityですが、「共同体」「地域社会」「地域住民」「集団」「一般社会」など様々な訳語が存在します。
まあ、あまり悩まずに「集団」やら「地域」と訳して、さっさと次の設問に移ったほうが良いとは思うのですが、文脈に沿ってうまく訳そうと思うと意外に悩むかもしれません。
なかには「コミュニティ」とそのままカタカナで訳した受験生もいたそうですが、まあ、和訳問題という特性を考えると、ちょっとグレーな気もします。
ここは日本語能力の高い受験生ほど、適切な訳語をどうしたら良いのか悩まれたかもしれませんが、多少違和感のある訳になっても、それで✖︎を食うことは経験上ありませんから、まずは解答用紙を埋めることに注力していただきたいと思います。
なお、favoriteについては直訳すると、「お気に入り」となりますが、「コミュニティがお気に入りの」では日本語として違和感がありますので、「コミュニティ(集団・地域)で人気の」「その地域に住む人々に気に入られている」などと言葉を添えられるとナチュラルな日本語になるでしょう。
それでは、解答例をご紹介いたします。
下線部(ア)の解答例
(ア)“You can’t say that!” I imagine someone sitting around an evening fire suddenly shouting to the community’s favorite storyteller.
敬天塾 解答例1
「そんなことを言ってはダメだ!」と、夕暮れの焚き火のまわりに座っている誰かが、その部族社会のなかで人気の語り部にいきなり叫んでいる光景を私は想像する。
敬天塾 解答例2
「あなたはそんなことを言ってはいけないよ!」。 夕暮れ時の焚き火を囲んで座っている誰かが、その地域の人々に気に入られている語り部に突如としてそう叫んでいるのを、私は思い浮かべる。
敬天塾 解答例3
「そんなことを言うな!」と、夕暮れ時に焚いた火のまわりに腰掛けている人が、部族集団で一番人気の語り手に急に大声で怒鳴っている情景を、私は思い浮かべている。
2025年度4B(ア)を解くために下線部以外も読んでおくべきだったか
逐語訳をする分には、下線部だけでも十分だったでしょう。
ただ、焚き火のまわりに複数の人がいて、storytellerの話を聞いている(第1段落末尾のlistener)情景を本文から読み取れると、「ああ、そういうことが言いたいんだな」というのがよくわかります。
communityの訳出も、下線部(ア)の直後にあるthe huntや、第2段落冒頭のancient storytellerから、原始時代の話でもしているのかなと推測できますので、文脈に合わせて意訳するなら、下線部以外もしっかり読み込んでおいたほうが良かったでしょう。
【下線部(イ)の和訳ポイントと和訳の工夫】それほど難しい構文や単語は使われていないのに、なぜかしっくり訳せない。これぞ、まさに東大4B!
構文レベル★☆☆
語彙レベル★★☆
訳出工夫度★★★
(イ)They silently “get it” and a bond is now formed between them. These few “insiders” have done what alert audiences would do throughout all succeeding generations.
いかがでしょうか。このレベルになってくると下線部だけを読んでも正確には訳せないはずです。
仮に下線部だけを直訳してみると、
(下線部だけを読んで直訳した駄作答案)
彼らは静かに「理解」し、彼らの間には今や絆が形作られた。これらの少ない「内部の人」は、あらゆる後の世代を通して警戒心の強い聴衆がするであろうことを既にやった。
いかがですか。何を言っているのか全然わかりませんよね(笑)構文は単純ではあるのですが、
①Theyとthemが指している対象が異なることを訳にどう反映すべきか
②insidersをどのように文脈に沿った形で訳出すべきか
③alert audencesをどのように文脈に沿った形で訳出すべきか
が差別化要素になってくると思います。
これらを理解するには、下線部(イ)の前と後ろの両方を読み込んでおく必要があります。
そこで、第2段落の流れをざっくりまとめてみるとしましょう。

いかがですか?だいぶ見通しが良くなりましたね。
下線部だけでも、「一応」日本語には訳せますが、まったく意味をなさない文でしたよね。
ですが、文脈のなかで下線部(イ)を把握しようと努めると、途端に真意がクッキリと浮かび上がってきます。
東京大学が4B英文和訳で求めているものは、構文解釈力+日本語能力+情景理解力の調和がなされた答案です。
文脈把握によって情景がわかっていても、語彙力といった日本語能力が欠けていれば、意図したものと異なる答案が出来上がってしまいます。
構文解釈力が伴わない読解だと、勝手な想像に基づく解釈を書き記すこととなり、それは作文と変わりなくなってしまいます。
それゆえに、三者のバランスが重要なのです。
下線部(イ)のTheyは語り手の意図を察したa small part of clanのことですね。
get itは、慣用表現でよく使われる「I got it(わかった)」の現在形で使っていますから、ここでは「理解する」「わかる」と訳せば良いわけです。
ちなみに、何がわかるのかというと、語り手が込めた言外の意味ですね。
そうして、自分の意図を理解した人たちとの間に共感が芽生えるわけですから、「絆」「つながり」のようなものが生まれるわけです。
そのことをa bondと言っているわけですね。
そのbondは誰と誰の間で芽生えたのかというと、もちろん語り手と語り手の意図に気づいた人たちであり、両者をbetween themとしているわけです。
つまり、主語の「They」とbetweenの後の「them」は指している対象が異なっているわけです。両者の違いを無視して、単純に「彼ら」と訳してマルをもらえるとは思えません。
ここで図解を試みたいと思います。

こうした理解者のことを、”insiders“と言っているわけです。
これを単に「内部の人」と言ったんでは、何を言っているかわかりません。
意訳しすぎも良くはありませんが、「仲間」とか「心を通わせられる人たち」とか「心の友」とか「理解者」とか「事情通」とか「消息筋」とかのように言い換えても問題ないように思えます。
では、alert audienceとは何でしょうか。
alertというと「警戒している」「油断のない」という意味がよく知られていると思いますが、「警戒している聴衆」だと意味がまるで通じませんよね?
まず、alert audiencesと”insiders”がやっていることは一緒だと言っているわけです。
そして、alert audienceがやったことが “read between the lines“(隠された真意を見抜き、行間を読むこと)なのです。
なぜ、彼らにはそれができたのでしょうか。
ボケっと聞いていたのでは、真意をつかむことはできませんよね。
「頭の回転が早い」「勘が鋭い」「頭が冴えた」と訳出するのが良さそうです。
chatGTPのようなAIに解かせても、こういう訳は出てきません。
本当に頭を使って、文脈把握を行なった人にしか紡ぎ出せない訳です。
このように脳みそに汗をかかせた思考を東京大学英語部会は受験生に求めているわけです。
もはや、この設問は芸術の域に達した問題です。
SNSで和訳問題の集大成と賞賛されるのも良くわかりました。
そのほか、訳出で注意すべきはsucceedingでしょうか。
くれぐれも「成功した」などと訳してはいけません。
文脈的にいきなりsucceeding generations「成功した世代たち」と言われても何を言っているかわかりませんよね。
successorで「後任」を意味することを思い出せたなら、succeedingの意味も推測できたのではないでしょうか。
それでは、ここで敬天塾の解答例を示したいと思います
下線部(イ)の解答例
(イ)
They silently “get it” and a bond is now formed between them. These few “insiders” have done what alert audiences would do throughout all succeeding generations.
敬天塾 解答例1
彼らは暗黙のうちに「理解」し、そうして今や語り手と彼らの間に絆が生まれている。こうした数少ない「心通じ合える理解者たち」は、後世のあらゆる世代にわたって、勘の鋭い聴衆たちがやってきたであろうことを行なったのである。
敬天塾 解答例2
彼らは何を言うわけでもなく「理解」し、その結果、双方の間には絆が芽生えている。こうした数少ない「仲間たち」は、後々のあらゆる世代において、頭の回転が早い聴衆たちがやってきたであろうことを行なったのだ。
敬天塾 解答例3
彼らは心の中で「真意をつかみ」、そうして、両者の間にはいまや絆がつくられている。こうした数少ない「事情通たち」は、そののち代々にわたって頭の冴えた聞き手たちがおこなったであろうことをやったのだ。
2025年度4B(イ)を解くために下線部以外も読んでおくべきだったか
はい、下線部以外を読まなくては、正確な訳出は不可能でした。
小手先のテクニックが使えない設問を出したい、そして、受験生になんとしても本文全体を読んでほしいという、東大教授の強い想いを感じ取れました。
和訳問題の王者は、これまで京都大学だと思っていましたが、京大とはまた別次元での難しさが東大4Bにはあるのだなと、作問をご担当された教授陣に敬意の念を抱きました。
とても素晴らしい問題だったと思います。脱帽です。
【下線部(ウ)の和訳ポイントと和訳の工夫】本問については下線部だけで真意を掴めた人もいたかもしれませんが、多くの受験生には難しかったのでは?
構文レベル★★☆
語彙レベル★★★
訳出工夫度★★☆
(ウ)The exciting tale of how the dangerous beast was skillfully trapped and killed is really ー as some listeners figure out ー a story about ridding themselves of their vicious leader.
いよいよ、4Bのラストです。
文章構造はいたってシンプルです。
このレベルの構文をつかめない方は、構文解釈用の問題集やスタサプの構文解釈講座を受けることをオススメします。
一応、ざっくりと図解をしますと・・

となります。要は、

という構造をしているわけです。
ここまでわかれば、あとは、文構造を意識しながら訳出はするのみです。
ridやviciousあたりの意味がわからなかった受験生が多いと聞きますが、ridはget rid ofという基礎英熟語から意味を連想することもできたでしょうし、viciousの意味がわからずとも、the dangerous beastと対になっていることに気付ければ、viciousはdangerousの類似表現ではないかと推測することもできたはずです。
なお、themselvesは複数形のlistenersを指していると言えます。
他に複数形の名詞が近くにはないからです。
また、riddingを本番の焦りのなかで、riding(乗ること)と混同された受験生が一定数いるようです。
意外に笑い話にできない話でして、4B英文和訳に限らず長文読解においても単語の見間違いで誤読してしまう方は、そこそこいます。
代表的なものを幾つかあげると、
cooperationとcorporation、
confirmとconform、
brakeとbreak、
farmとfirm、
desertとdessert、
purseとpursue、
peaceとpiece、
loseとloose、
moralとmorale、
lackとluck、
adaptとadopt、
properとprosper、
wanderとwonder、
weatherとwhether、
conservationとconversation、
religionとregion、
expectとexcept、
besideとbesides、
natureとnurture、
collectとcorrect、
glassとgrass、
industrialとindustrious、
deriveとdepriveあたりが誤読することの多い単語群だと思われます。
いかがでしたか?
なんだか、ゲシュタルト崩壊でも起きそうな気持ちになりますよね(笑)
自宅など、自分にとって居心地の良いところで、ゆったりと英文を読んでいるときにポカミスを犯すことは少ないものです。
ですが、試験会場は基本的に居心地の悪い場所ですから、落ち着いて取り組むことを阻害するものがわんさかあります。
そうした状況や環境を想定した演習を積むように心がけましょう。
詳しくは、知恵の館の連載記事『合格の呼吸』や『勇者に贈ることば』シリーズでも詳述しておりますので、ぜひお役立てください。
それでは、解答例をご紹介いたします。
下線部(ウ)の解答例
(ウ)The exciting tale of how the dangerous beast was skillfully trapped and killed is really ー as some listeners figure out ー a story about ridding themselves of their vicious leader.
敬天塾 解答例1
いかにして危険にあふれた獣を巧妙に罠にかけ殺めたのかというハラハラドキドキする物語は、実のところ、一部の聞き手たちには悟られているように、自分たちの残虐な支配者を放逐することを題材にした物語なのである。
敬天塾 解答例2
聞き手の中には気付いている人もいるようだが、危険な獣をどのようにうまく罠にかけて殺したのかという内容の面白い物語は実際には、自分たちの横暴な長(おさ)を倒すことにまつわる話をしているのである。
2025年度4B(ウ)を解くために下線部以外も読んでおくべきだったか
対比構造がわかりやすい文ですから、下線部だけを読んでも、ある程度の完成答案は紡ぎ出せたかもしれません。
ですが、下線部(ウ)の直前に書かれていた言外の意味(隠されたメッセージ)についての記述をしっかり読み込んだ人の方が、はるかに、下線部(ウ)でいうところの獣は独裁者をたとえたものだと気付きやすくなると思います。
せめて下線部の直前にある3〜4行だけでも読むだけでも、理解度が格段に上がったことでしょう。
以上をもって4Bの解説を終えたいと思います。
本文を読み終えた方は、改めて第1段落の冒頭で書かれていたCensorship may be as old as literature itself.の意味を考えてみてください。
本文全体を通して読んだとき、この一文が何のために冒頭で提起されたのか伏線回収ができることでしょう。
考え過ぎかもしれませんが、どことなく今年度の2A自由英作文のテーマにも通ずるものはあったように思えてなりません。
なお、下線部を先読みしてから本文を熟読するのか、
本文を熟読してから下線部和訳に挑戦するのか、
下線部を含んだ段落ごとに区分けして分析検討するのか、
下線部だけ読んで不明瞭な時には本文を拾い読みしていくのかは、
残された時間や読解速度や設問文章との相性によっても変わってくると思いますので、一概にこれをやれとは言いづらいところがあります。
この4Bをリスニングの前と後のいずれでやるのか、
何分で解くつもりなのか。
その時の精神状態などによっても変わってきます。
敬天塾の教材を活用しながら大問別対策が終わった段階で、年度別にフルセット演習を実施し、時間に追われるなかで頭をうまく切り替えられるかを分析してみるのも学びが大きいと思います。一度解いたことのある問題でもです。
(雑感)
東大英語は本当に脳みそをフルに使う問題ばかりです。
たかが英語の問題とおっしゃる方も世の中にはいますが、ぜひ一度解いてみてください。
様々なメッセージが込められた東大英語は英検やTOEICなどの資格試験とは比べ物にならない程に重たく、そして面白い問題でもあります。
作問者の先生方を心から尊敬申し上げます。
【さらに深く学びたい方のために】
敬天塾では、さらに深く学びたい方、本格的に東大対策をしたい方のために、映像授業や、補足資料などをご購入いただけます。
ご興味頂いたかたは、以下のリンクからどうぞご利用下さい。
映像授業【東大英語 第4問B 英文和訳】
他年度の過去問に対して、これでもかと噛み砕いて説明した《実況中継》の解説もございます。
↑ まずは目次と無料部分だけでもどうぞ。

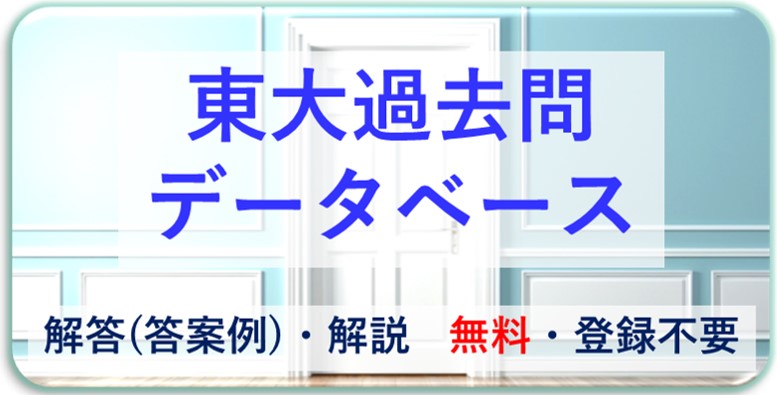


解説2025-300x161.jpg)
とても丁寧でわかりやすい解説でした。ありがとうございます。ただ(ア)でsuddenly の訳出が漏れてます!
ありがとうございます。
答案例を修正いたしました。ご指摘ありがとうございました。