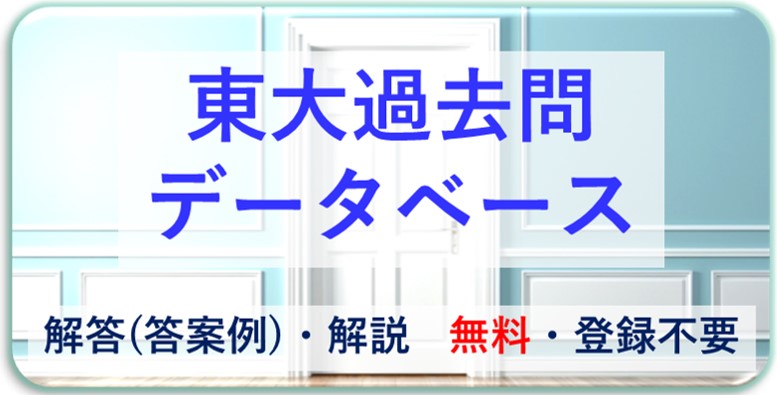2021年東大日本史(第四問)入試問題の研究
講評
第4問 華族令と高橋是清
難易度 標準
珍しい華族令に関する問題。
衆議院の方が(比較すると)話題になりやすいような気がしますが、憲政史を見るときには貴族院も重要です。
設問Aでは設立時の問題で、設問Bではルールに従って動いた高橋是清の意図を国内政治の状況と絡めて論ずる問題でした。
設問Aも、設問Bも、史料から一部の意図が読み取れてしまうため、部分点は取りやすい問題だと思います。
そういう意味では易問ですね。
ただ、合計6行というのが(最近の東大にしては)ちょっとだけ多いのと、3行でも字数制限は厳しい印象があったので、全体の難易度は標準で良いかなと思います。
当日解いた所感
難易度 やや易~標準
定番ではないけど、難しくはない。
東大らしいと言えば、東大らしい問題です。
設問は華族令の話です。
貴族院と華族、誰を華族に入れるか入れないかといった話。
有名な話ですが、衆議院と貴族院を創るときに、華族令が制定されました。
設問Bは、高橋是清の話。
1924年に衆議院に立候補するのですが、その時にわざわざ、わざわざ華族の戸主を辞めるんです。貴族院議員も辞して隠居する。そうしないと、衆議院に立候補できない。という資料を読み取る問題でした。
資料からある程度のヒントを得て、自分で知識や考えを補充して書く問題です。
ちなみに、高橋是清はデフレを脱却させた首相だから個人的には好きな人物です。
ちゃんと憲法のルールに則って、正々堂々と戦った姿勢を見せたことが読み取れるので、東大はそういう政治家を求めているのかもなぁとも思いました。

解説2021.jpg)